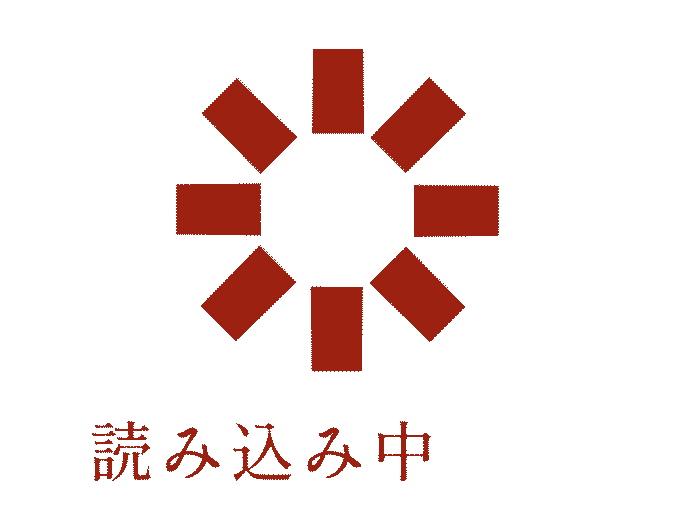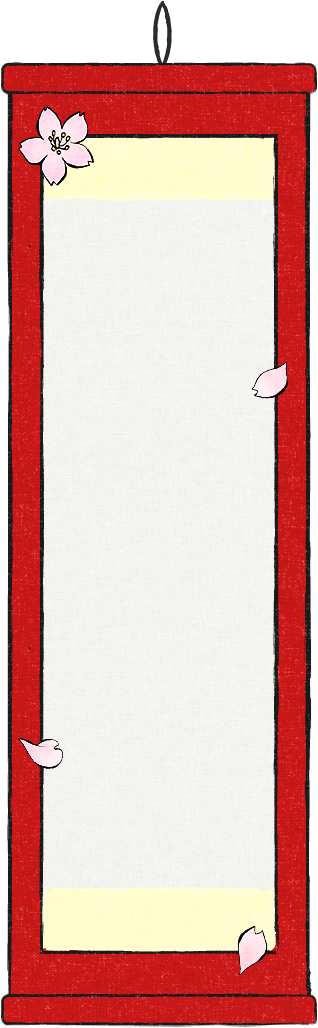八月の新作『無明ノ月』は、もうご覧いただけましたでしょうか?
本作では歌詞に仏教用語を多用しており、「渇愛」をテーマに制作しました。
渇愛とは「喉の渇いた者が激しく水を求めるような衝動」のことで、強い欲望や執着を指します。この渇愛によって人間は動き、迷い、「苦」を生じさせるとされます。この欲望を制御して、苦しみから解放された状態(=涅槃)に至ることが、仏教における実践的な目標です。
渇愛は3つに分類されるのですが、「花ノ札紀」登場人物たちの行動も、概ねそれらに当てはめることができます。
1.欲愛(物事への執着、色愛)
2.有愛(生存することへの執着)
3.無有愛(存在したくないという欲)
そして、本作のタイトルにも用いられた「無明」は、最も根本的な煩悩である「真理への無知」を意味します。釈尊の説く真理を「知らない」からこそ渇愛が生じ、迷い苦しむことになるのです。
では、その真理とは何かというと、三法印と呼ばれる3つの教え(諸行無常・諸法無我・涅槃寂静)です。このなかで「諸行無常」は「万物は常に変化しており、永遠などない」という意味を持ちます。これに反して変化を拒み、受け入れられないからこそ欲望や執着が生まれる・・・というわけです。
ちなみに諸法無我は「万物は因縁によって生じており実体がない」こと、涅槃寂静は先ほども登場した「苦のない静かで穏やかな世界」を指し、仏教の教えが目指す最終地点です。
無明(真理への無知)→渇愛(執着)→苦(つらさ)
今回は「渇愛と無明」にフォーカスしてものすごく簡潔にまとめてしまったので、詳しく知りたい方は、ぜひご自分で調べてみてください。
実は「花ノ札紀」全体にも、仏教思想への問いかけが根底に流れています。「愛」することは地獄を生むのか?累伽が自身への問いかけのために狂わせた世界で、人間たちは「愛」をどのように捉え、見つけていくのか?そして、累伽自身に「渇愛」はないのか・・・?
これらのキーワードが、作品を掘り下げていく鍵になるかもしれません。
【キーワード】
渇愛、無有愛、諸行無常、輪廻
曲中にも取り入れた「般若心経」についても触れたかったのですが、長くなってしまうので、またの機会に。